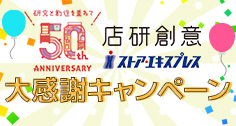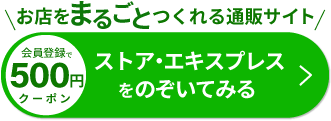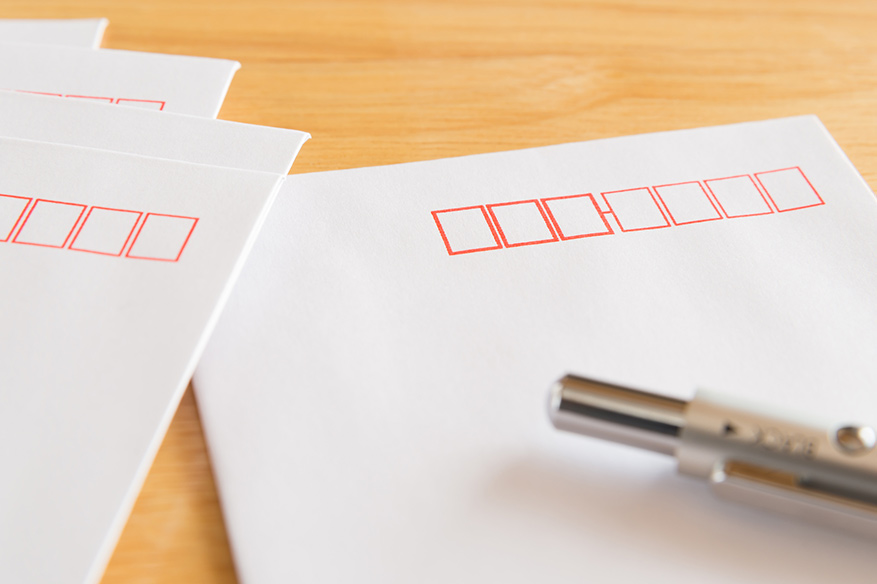【目次】
■こどもの日とは

こどもの日は、国が定める国民の祝日のひとつです。日本の「国民の祝日に関する法律(祝日法)」では、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」日と定義しています。※
「こどもの日は男の子のお祝いをする日、ひな祭り(桃の節句)は女の子のお祝いをする日」とイメージしている方は多いかもしれませんが、実は男女関係なく、全ての子どもをお祝いする日です。
※出典:内閣府「国民の祝日」について
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
■こどもの日と端午の節句の違い

5月5日のこどもの日は、端午の節句とも呼ばれます。「節句」は季節の節目を意味する言葉で、端午の節句は中でも特に重要な「五節句」のひとつです。
五節句には他にも、1月7日の人日(じんじつ)や、3月3日の上巳(じょうし)、7月7日の七夕(たなばた・しちせき)、9月9日の重陽(ちょうよう)があります。
古代中国では、端午の節句に合わせて、病気や災いなどの邪気を払うための行事が行われていました。奈良時代になると日本に伝わり、宮中行事として行われるようになります。
その行事で使われていた「ショウブ(菖蒲)」の読み方が「尚武(武道を重んじること)」と同じことから、江戸時代頃に端午の節句が「男の子の成長を祝う日」になったそうです。
その後、第二次世界大戦後の1948年になると、5月5日がこどもの日として、国民の祝日に制定されました。
同じ日なので勘違いされやすいですが、こどもの日は「性別関係なく子どもの成長を祝う日」で、端午の節句は「男の子の成長を祝う日本の伝統行事」という違いがあります。
■海外にもある「こどもの日」

こどもの日は日本だけのイベントではなく、世界中の国々で設けられています。世界で最も早くこどもの日を定めたのはトルコといわれていて、1920年には4月23日をこどもの日と制定したそうです。
その後、1954年には国連が11月20日を「世界こどもの日」と定めていますが、具体的な日付は国によって異なります。
例えば、メキシコは4月30日、インドは11月14日、ブラジルは10月12日を、こどもの日として定めています。
■こどもの日に行うこと

日本におけるこどもの日の定番といえば、鯉のぼりや五月人形を飾ったり、しょうぶ湯に入ったりする風習でしょう。しかし、それらの風習はなぜ行われているのでしょうか。
一般的なこどもの日の風習と、それぞれに込められた意味や由来をご紹介します。
鯉のぼりを飾る
こどもの日になると、大きな鯉のぼりが上がっている様子を目にすることが多いでしょう。鯉のぼりを飾る風習は、江戸時代に始まったとされています。当時、武士階級では、男の子が生まれると幟(のぼり)や旗指物(自分の存在や所属を知らせる旗)を玄関に立てて祝う風習がありました。町人の間では、こうした武家の風習にあやかり、紙で作った鯉の形ののぼりを揚げるようになったことが、鯉のぼりの由来とされています。
旗ではなく鯉を使うのは、滝を登った鯉が竜になったという中国の故事にちなみ、「困難を乗り越え、立派な子に育って欲しい」という願いを込めているそうです。
竿の上には、邪気を払うための吹き流しや矢車、神様に気付いてもらうための天球などを飾ります。
また、江戸時代は鯉を1匹飾るのが主流だったようですが、現在は真鯉(父親)、雛鯉(母親)、子鯉(子ども)の3匹を飾るのが一般的です。
五月人形や兜を飾る
子どもの健やかでたくましい成長を願うために、五月人形や兜を飾るのも、こどもの日の定番です。邪気を払う、病気や事故から子どもを守るといった意味を込めた飾りで、武家社会の風習が由来とされています。
五月人形には、子どもに代わって災いを引き受ける「身代わり人形」の意味も込められているため、人に譲り渡すのは縁起が悪いといわれます。使わなくなったら他人に渡すのではなく、供養に出すようにしましょう。
しょうぶ湯に入る
しょうぶ湯(菖蒲湯)に入るのも、こどもの日の定番です。中国では昔から、香りが強いショウブは邪気を払う植物として使われてきました。そこから転じて、厄や災いを遠ざけるために、しょうぶ湯に入る習慣が生まれたそうです。
また、ショウブを浸したお酒を飲んだり、家の軒下に飾ったりする風習もあります。