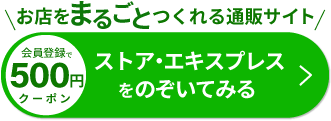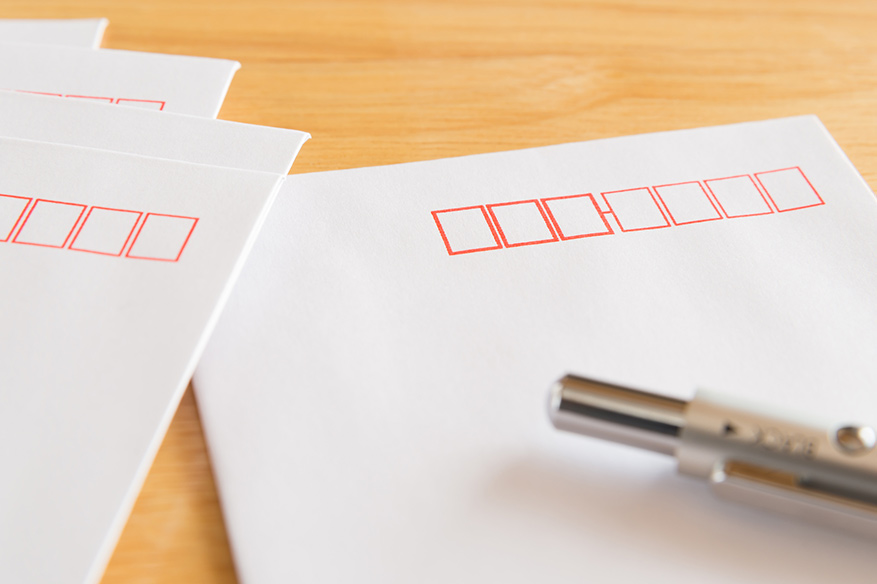【目次】
■七夕とは?

七夕(たなばた・しちせき)とは、季節の節目(節句)に行われる年中行事のことです。3月3日の桃の節句(ひな祭り)や、5月5日の端午の節句(子どもの日)などと並んで、節句の中でも重要な「五節句」のひとつに数えられます。
7月7日の夜に、織姫(おりひめ)と彦星(ひこぼし)が天の川を渡って1年に1回だけ出会えるという伝説にちなみ、日本各地でさまざまな行事やお祭りが行われています。中でも、宮城県の「仙台七夕まつり」や、神奈川県の「湘南ひらつか七夕まつり」などが有名です。
現在日本で使われている「太陽暦」だと、7月7日は曇りや雨の日が続く梅雨の時期で、天の川を見られないことも多いです。しかし、古くは現在の8月上旬から下旬にあたる、旧暦の7月7日に行事が行われていました。この時期だと、全国的に梅雨明けしていて月明かりの影響も少なく、晴れていれば、天の川が流れるきれいな夜空を眺めることができます。 旧暦の七夕は「伝統的七夕」と呼ばれており、先述の「仙台七夕まつり」をはじめ、現在も旧暦に合わせてイベントを行うところもあります。
■七夕の由来

日本で現在親しまれている七夕は、日本古来の風習や中国由来の伝説が掛け合わさってできたものとされています。七夕の由来とされている、3つの風習や伝説をご紹介します。
・織姫と彦星の伝説

七夕で最も有名なのが、織姫と彦星の伝説ではないでしょうか。中国ではそれぞれ織女(しゅくじょ)と牽牛(けんぎゅう)と呼ばれます。
天空の主である天帝の娘で、機織りの名人だった織女は、牛飼いの牽牛と恋に落ちて結婚しました。しかし結婚後、働き者だった2人は仕事をしなくなり、それに怒った天帝は2人を天の川の両岸に引き離します。
悲しみに暮れる織女を不憫に思った天帝は、年に一度だけ2人を合わせるように計らった、というのが伝説のあらすじです。
織姫(織女)はこと座の一等星「ベガ」、彦星(牽牛)はわし座の一等星「アルタイル」という星にあたります。旧暦7月7日は、天の川を挟んでベガとアルタイルが最も輝いて見えることから、この伝説が生まれたそうです。
また、ベガとアルタイルに、白鳥座の一等星「デネブ」を加えた3つの星は「夏の大三角」と呼ばれ、広く親しまれています。
・乞巧奠(きこうでん)
笹飾りに短冊を吊るして願い事をする風習は、中国の「乞巧奠(きこうでん)」と呼ばれる儀式が由来とされています。乞巧奠とは、祭壇に針などを供えて星に祈りを捧げ、織姫にあやかり「機織りが上達するように」と願う中国の風習のことです。
当初は機織りの向上を願うものでしたが、徐々に手芸や詩といった芸術全般の上達を願う意味が含まれるようになりました。
この風習は奈良時代(710~784年)頃に日本に伝わったとされ、現存する日本最古の和歌集『万葉集』でも、七夕にちなんだ和歌が詠まれています。
当初は宮廷行事として行われていましたが、時代とともに庶民にも広がり、江戸時代には全国各地で七夕まつりが開催されていたようです。
・棚機(たなばた)
日本では古くから、祖先を祭る前の禊(みそぎ)がお盆の一環として行われていました。女性が着物を織って棚にお供えし、豊作を願ったり人々の穢れを払ったりするという風習です。
選ばれた女性は「機織津女(たなばたつめ)」と呼ばれ、機織りには「棚織(たなばた)」という機織り機が使われていました。
七夕が「たなばた」と当て字で読まれるのは、この風習が由来とされています。
■七夕の飾りの意味

七夕の際は、願い事を書いた短冊や、折り紙で作った七夕飾りを笹に吊るすのが一般的です。実は、それぞれの飾りにも意味が込められています。短冊をはじめ、七夕の飾りに込められた意味をご紹介します。
・短冊が5色の理由
笹に吊るす短冊は、古くは和歌を書いて学問や書道などの上達を願っていました。現在は、学問などに関わらず、個人の願い事を書いて吊るします。現在はあまり意識されることがないものの、七夕飾りの短冊は赤・黒(紫)・青・白・黄の5色が一般的です。
七夕飾りの短冊が5色なのは、中国の五行説が影響しています。五行説とは、世の中のすべては火・水・木・金・土のいずれかに当てはまり、それぞれが影響し合っているとする自然哲学の考え方です。火が赤、水が黒、木は青、金が白、土が黄色に対応します。
日本では、黒色は縁起が悪いという理由から、高貴な色である紫に変化しました。また、日本語の青は緑色も表す言葉だったため、緑色が含まれるようになったそうです。
・短冊以外の七夕飾りの意味
七夕では、短冊以外にも吹流しやくずかご、投網、折り鶴といった、さまざまな飾り物を吊るします。短冊以外の七夕飾りと、それぞれに込められた意味は、以下の通りです。
【吹流し(ふきながし)】
垂らした織糸を模した飾りです。織姫を象徴し、手芸や機織りの向上を願って飾ります。
【くずかご】
七夕飾りを作り終えた後に出る紙くずを入れる飾りです。ものを粗末にしないで役立てる倹約の気持ちや、清潔さを育てる意味を持ちます。
【投網(とあみ)】
投網とは魚を取るための網のことで、大漁を祈願して飾ります。
【折り鶴】
家内安全や長寿を願い、家長の年の数だけ折ります。千羽鶴にする場合もあるようです。
【巾着(きんちゃく)】
古くはお金を入れていた巾着は、貯蓄や金運の上昇を願う飾り物です。お金が逃げないように、口の部分をしっかり結びます。また、巾着ではなく財布を飾る場合もあります。
【紙衣(かみごろも)】
折り紙で作った人形や着物が紙衣です。機織津女が織った着物を模していて、裁縫の上達などを願います。また、病気や災いが起こらないようにという厄除けの意味や、子どもの健やかな成長を願い身代わりとして流す形代(かたしろ)の意味合いもあるとされています。
七夕飾りは、古くは高くに掲げるほど星に願いが届きやすいと考えられていました。安全面の観点などから難しいかもしれませんが、少し高めの場所に飾ってみるのも良いかもしれません。
■七夕の行事食

ハロウィンのカボチャやクリスマスのケーキ、お正月のおせち料理やお雑煮など、年間行事には「行事食」と呼ばれる定番の食べ物が見られます。馴染みが薄いかもしれませんが、七夕は索餅(さくべい)と素麺(そうめん)が行事食です。
索餅とは、米粉や小麦粉を練ったものをひねって揚げた、中国由来のお菓子です。縄のような見た目から、麦縄(むぎなわ)とも呼ばれます。中国では、無病息災を祈願して7月7日に索餅を食べる習慣があり、それが日本にも伝わりました。
やがて、時代とともに索餅は同じ小麦粉から作られる素麺へと変化し、現在も風習として残っています。
また、健康祈願や無病息災だけでなく、「天の川に見立てた」「織姫にあやかり、素麺を糸に見立てた」など、素麺を食べるようになった由来はいくつか説があります。
行事食ではありませんが、ちらし寿司も七夕定番の食べ物です。お寿司は縁起のよい食べ物とされ、日本では祝い事の日などにお寿司を食べる習慣が根付いています。