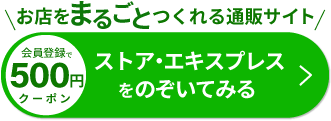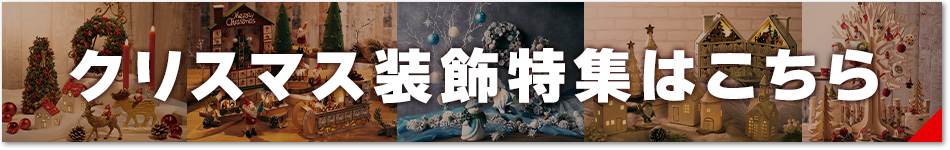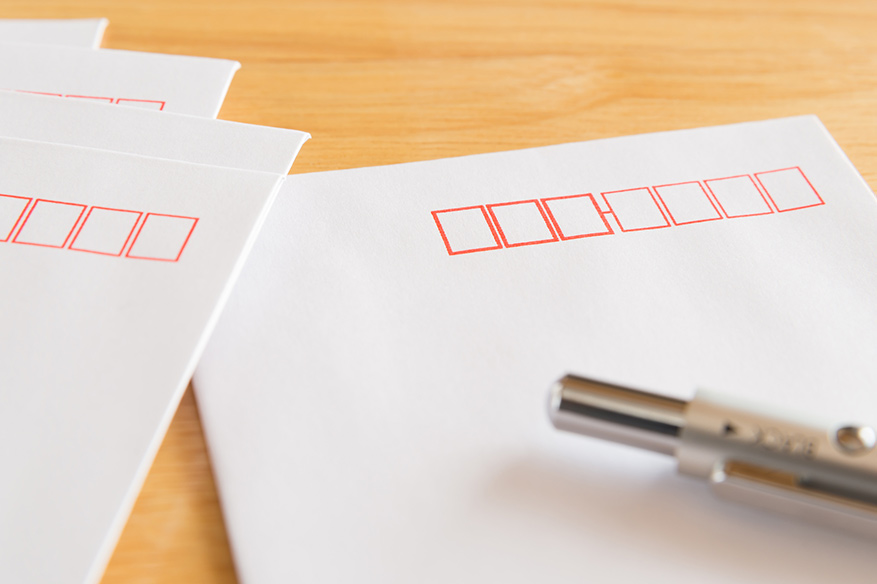【目次】
■クリスマスリースとは?
・クリスマスリースの起源と歴史
紀元前2世紀、古代ローマの冬祭りサートゥルナリアでは、常緑樹の枝を丸く束ねた「コロナ」(冠や花輪を意味する言葉)を玄関に掛け、寒い季節を乗り越えて春が戻り、命が途切れないようにと願いました。詩人ウェルギリウスが月桂樹やオリーブをほめたたえた話も、枯れない葉に「守ってくれる力」があると信じられていたことを示しています。
ポンペイ遺跡の壁画には、ブドウのつるを輪にした飾りが豊かさの女神オプスへのお供えとして描かれています。丸い形は太陽が毎日昇って沈む循環、つまり再生を表すと考えられました。博物学者プリニウスは、その著書の中で植物が病気を遠ざける効能を持つことを示唆しており、リースはおしゃれなだけでなく、魔除けと豊作祈願を兼ねる生活道具だったわけです。

4世紀にローマ帝国がキリスト教を国教にすると、異教の習慣だったリースはキリスト教の文脈でも用いられるようになり、その常緑樹の輪が持つ永遠性は、キリストの永遠の愛や生命の象徴とされたり、また、そのいばらの冠と結びつけられる解釈も生まれたりしました。中世になるとヒイラギのリースがミサの本やステンドグラスに登場し、地域社会においてリースが季節の節目や共同体の結束を示す役割を果たすようになっていったとされています。19世紀のイギリス・ヴィクトリア朝では、暖かい温室と新聞・雑誌の影響でリースが一気に大衆化します。1848年の『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』が王室のリースを紹介すると売れ行きが急増し、蒸気船でアメリカに渡った大量生産品は1890年代のクリスマス商戦で急速に普及し、売上を大きく伸ばしました。
日本に初めてリースが入ったのは1870年代で、宣教師が持ち込みました。明治屋や丸善が銀座で販売を始め、戦後にはアメリカからの輸入が盛んになり、普及に拍車がかかりました。1980年代のテレビCMがブームを後押しし、今では100円ショップから高級ブランドまで幅広く手に入ります。
こうしてリースは古代ローマの農耕まじないから現代日本のインテリア雑貨へ姿を変えましたが、「命が続くように守ってほしい」という願いは2000年以上変わらず受け継がれています。
■リースに込められた意味

・魔除けや幸福祈願の象徴
ヨーロッパでは、ヒイラギのとがった葉が悪いものを刺して家に入れない「とげのおまもり」として親しまれてきました。中世の家庭では病気を運ぶ風を防ぐため玄関や窓辺にヒイラギを飾り、家畜小屋にも同じ枝を置いて人も動物も守ろうとしました。現在もイギリスをはじめとする一部の地域では、ヒイラギを戸口に飾ることで魔除けとし、一年を無事に終えられるようにと願う古くからの習慣が残っています。目に見えない不安を葉のとげに託して外にとどめる――その素朴な願いが何百年も続いている点に、暮らしと祈りの根強い結びつきを感じます。
豊作を願う飾りとしては、固い殻で種を守る松ぼっくりとたくさんの実を付けるブドウが代表的です。ドイツの秋祭りでは子どもたちが特大の松ぼっくりをかごに入れて行列し、「来年も畑が実りますように」と歌をうたいます。イタリアのワイン産地では収穫後のブドウのつるを輪にして台所につるし、翌年の収穫まで眺めながら家族で感謝を語り合います。輪が乾いていく過程そのものが「実りは土に返り、また芽を出す」という物語になり、子どもにも自然の循環を教えてくれる道具になっています。
日本の正月飾りも「悪いものを遠ざけ、良いものを呼ぶ」という考え方は同じです。クリスマスが終わったらベルや赤い玉を外し、松ぼっくりや稲穂、赤い水引を付け足すだけで洋風リースが和風のしめ飾りに早変わりします。常緑の松は長寿を、稲穂は食べ物に困らない暮らしを象徴するので、飾る位置を変えずにそのまま年越しができる点も忙しい年末には助かります。
こうしたアレンジが浸透したことで、リースは冬だけの飾りではなく「一年中、家族を守るお守り」として広がっています。最近のSNSでは南天の実やドライオレンジを加えた和洋ミックス作品が人気です。多くの投稿が「子どもが元気に育ちますように」「仕事が順調に進みますように」と願いを書き添え、リースがインテリアを超えて“思いを託す場所”になっていることがわかります。手間も費用もわずかながら、意味を知って飾るだけでドアを開け閉めするたびに小さな安心感が生まれる――これこそが魔除けと幸福祈願の役目が今も愛される理由です。

・リースの輪が表す永遠の愛
リースが輪になっているのは、始まりも終わりもない形で「ずっと続く」という気持ちを表すためです。切れ目のない線は家族や友だちとのつながりが絶えないことを願う象徴になります。玄関に飾れば、出入りするたびに「この家の絆はこれからも長く続く」というメッセージをさりげなく伝えてくれます。
キリスト教の考え方では、神の愛は見返りを求めず永遠に続くとされ、一筆書きの輪を描くリースは、その終わらない愛を目に見える形にしたものです。だからこそクリスマスシーズンにリースを掲げると、「神さまのやさしさに包まれている」という安心感を感じやすくなるのです。
最近では、この「終わらない輪」という意味を活かし、ホスピスで患者さんの写真やカードをリースに差し込んで思い出を共有したり、地域のワークショップで参加者がそれぞれのオーナメントを付け足して共同作品を作ったりする取り組みが増えています。輪に想いを重ねることで、人と人の心を結びつけるツールとしてリースが新しい役割を担いはじめているのです。

・色や素材が持つ象徴的な意味
クリスマスリースの定番色である赤・緑・白・金は、見た目以上に気持ちや行動に作用します。赤はやる気と活気を引き出し、緑は森林浴のように心を落ち着かせます。白は空間を明るくして清潔感を伝え、金は高級感と祝祭ムードを添えます。色の面積配分を意識するだけで、玄関や室内の雰囲気は大きく変わります。
使用する素材にも意味があります。常緑樹は「永遠の命」、コットンフラワーは「ぬくもりと母性」、メタリックオーナメントは「富や成功」を象徴します。こうした文化的背景を理解しながら組み合わせると、単なる飾りがストーリーを語る存在へ変わります。
最近は環境配慮型の素材も主流になっています。リサイクルガラスのオーナメントやFSC認証の木製ベースを選べば、見た目を損なわずに廃棄物や伐採を減らせます。大手メーカーもリサイクル比率を高める方針を打ち出し、エシカル消費を後押ししています。
赤をフォーカルポイントに置き、緑と白で安定感をつくり、金で輝きを添えます。そこへ常緑樹とコットンをベースにリサイクルガラスの飾りを散らせば、低予算でも物語性のある上質なリースが完成します。意味を理解して作れば、訪れる人と対話するアートになります。
■クリスマスリースの飾り方

・玄関ドアや壁に飾る方法
ドアや壁の素材を確認してから取付金具を選ぶと失敗しません。スチール製なら強力マグネット、木製なら細いピンか短いビス、ガラスやタイルには吸盤フックが相性抜群です。
屋外設置は「防錆」「撥水」「耐風」の三つがそろった金具が安心。重さ500g以内のリースなら耐荷重1kg以上のフックを目安にすると落下リスクを大幅に減らせます。
賃貸住宅で穴あけが心配な場合は、剥がせるコマンドフックや極細ピンを選べば壁へのダメージは最小限。直径20cm程度の軽量リースは画鋲一本でも固定できます。
取り付け前に壁をアルコールで脱脂し、貼り付け後は24時間荷重をかけずに養生すると粘着力が最大化します。撤去時はドライヤーで温めながらゆっくり剥がし、跡を濡れ布で拭けば原状回復も簡単です。
マグネットセット、コマンドフック、吸盤フック、いずれもホームセンターや100円ショップで手に入るので、低予算で取り付けられます。
・スワッグやタペストリーとの組み合わせ

垂れ下がる形のスワッグをリースと並べると、視線が上から下へ自然に流れ、リースの丸い中心にも目が集まります。コツはドアや壁の中央にリースを掛け、そこから20~30cm下にスワッグを少しずらして取り付けること。スワッグの長さはリースの約1.5~1.8倍にすると、見た目のバランスがプロが作ったように整います。同じ葉やリボンを両方に使えば統一感も簡単に出せます。
背景に布のタペストリーを合わせると、全体がぐっとおしゃれになります。たとえば生成りのリネン+ユーカリのグリーンで北欧風、赤いタータンチェック+松かさでクラシック、マクラメ編み+ドライオレンジでナチュラルなど。タペストリーの主な色をリースにも3~4割ほど繰り返すと、色がちぐはぐにならずまとまります。
スワッグ、リース、タペストリーの3つを組み合わせれば、縦・横・奥行きの立体感が生まれ、限られた壁でも印象的なコーナーを作れます。ゲストの目に残る写真映えスポットになるので、家やお店の入り口を簡単に格上げできるアイデアです。
・季節感を活かしたコーディネート
たとえばネイビーやシルバーといった冬の寒色系を、モミやヒイラギの深緑と組み合わせると、視覚的な“冷たさ”が程よく緩和され、同時に凛とした高級感が生まれます。リース全体の色配分は深緑70%、ネイビー20%、シルバー10%を目安にすると、見た目のバランスが安定します。マット質感のネイビーボールオーナメントをリースの外周に散らし、中心部にシルバーの細リボンをスパイラル状に巻き込むと、金属光沢が雪の結晶のように輝き、夜間のライトアップでも映えます。
冬ならではの食材や植物を取り入れると、見た目だけでなく香りや触感でも季節を演出できます。みかんをスライスして低温オーブンで2時間ほど乾燥させた「ドライシトラス」は、鮮やかな橙色とほのかな柑橘の香りが特徴です。加えて、ふわふわのコットンボールを3~4個ポイント使いすると、雪のような柔らかさが生まれ、思わず触りたくなるような魅力がプラスされます。
季節が進み、立春を迎える頃にはリースの一部を差し替えて春の雰囲気へシフトさせましょう。パンパスグラスをリース下部に扇状に添えると、風になびく軽やかさが加わります。さらに、ミモザの小さな黄色い房を散らすと一気に春めいた印象になり、ネイビーやシルバーとのコントラストで華やかさが際立ちます。既存の深緑ベースを残したまま差し替えパーツを加えるだけなので、作業時間は15分程度。季節ごとの素材を少量ずつ入れ替える“シーズンブリッジング”を実践することで、ひとつのリースを一年中楽しめます。
・お正月飾りへのアレンジ
クリスマスリースをお正月飾りにアレンジする方法は、既存の土台を再利用することで、手軽に季節をまたぐ装飾が可能です。まず、ベルやオーナメントなどクリスマス特有のパーツを取り除き、残った常緑の土台に、南天の実を差し込み赤いアクセントを加えます。次に、水引を巻いて結び目を整え、金色や白色の紙垂(しで)を加えれば、迎春らしい神聖な雰囲気が生まれます。稲穂や竹細工の輪飾りを組み合わせると、さらに立体感のある和風リースに仕上がります。
このアレンジのメリットは大きく二つあります。一つは、廃棄物を最小限に抑える「サステナブル」な取り組みであること。そしてもう一つは、洋風のリースが持つ「永遠性」や「家族の絆」といった意味合いと、日本のしめ縄の「魔除け」や「豊作祈願」の意味合いが融合することです。これにより、玄関先が国際色豊かな祝祭空間へと変わり、「一年の終わりと始まりを連続的に捉える」というメッセージが強まります。忙しい年末に新たな飾りを準備する手間も省け、一年中家族を守る「お守り」としてのリースの役割を継続できる点も魅力です。
■まとめ
クリスマスリースが単なる装飾品ではなく、古代から現代に至るまで脈々と受け継がれてきた深い歴史と意味を持つアイテムであることを解説しました。魔除けや幸福祈願、豊作への願い、そして家族や友との尽きることのない絆や永遠の愛といった普遍的なメッセージが、その輪の形や使われる素材、色に込められています。
現代においては、手軽な取り付け方法や他の装飾との組み合わせ、季節ごとの素材の取り入れ方、さらにはお正月飾りへのアレンジなど、多様な飾り方が提案されています。これにより、リースは特定の季節だけに限定されず、「一年中、家族を守るお守り」として、また日々の暮らしに彩りや小さな安心感をもたらす存在として、その役割を広げています。
皆様も本コラムでご紹介したリースの知識や飾り方を参考に、想いを込めたリースを飾ってみてはいかがでしょうか。玄関にリースを掲げることは、訪れる人々に温かい歓迎を示すだけでなく、ご自身の心にも豊かな気持ちと希望をもたらすことでしょう。